この連載はOSSコンソーシアム データベース部会のメンバーがオープンソースデータベースの毎月の出来事をお伝えしています。この連載は、今年2025年の夏に満10歳を迎えます。2025年もOSSデータベース取り取り時報をよろしくお願いいたします。
OSSデータベースを組み込んだプロダクトの事例〜なぜそれを選んだ?@OSC大阪
1月25日に大阪で開催されたオープンソースカンファレンス 2025 Osaka
前回の再掲ですが、その概要です。OSSのDBMSは、カスタムアプリ
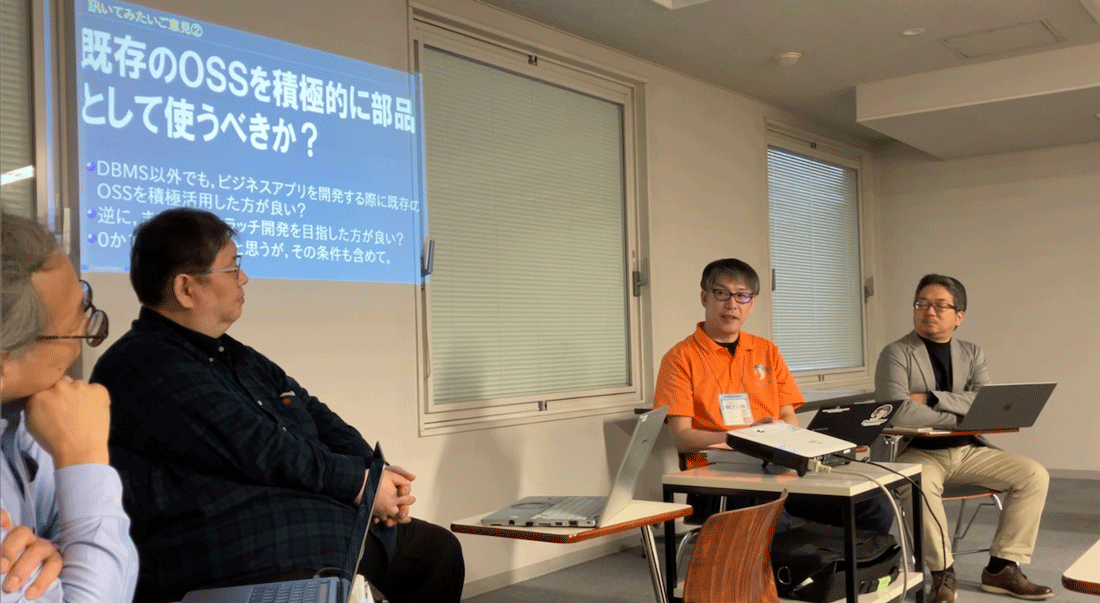
今回はここで紹介された2つの事例での、DBMSやプラットフォームの選択に関する部分を中心にお知らせします。
複数のDBMSに対応したプリザンター
まず、インプリム内田さんによる、ノーコード開発ツールのプリザンターの概要とデモからスタートです。わずか数分でアプリ機能を開発するデモを見せられるのは、ノーコードツールが本領発揮した部分でした。
プリザンターでは最初のDBMS選択はSQL Serverでした。当初の稼働環境がWindowsサーバだったこともあり、Windowsを使っている顧客がサポートをちゃんと付けてくれそうなものとしてSQL Serverを選択されたとのこと。
その後にPostgreSQLとMySQLにも対応しましたが、複数種類のDBMSに対応する苦労はなかったのでしょうか。プリザンターの製品内部ではORマッパー的なDBにアクセスする層を集約して開発しているので、異種DBMSに対応する際には、その部分だけ見直しや拡張することで解決しているようです。元々DBMS固有の機能に依存する部分は少ないことが幸いしたという面もあったそうです。ただ、全文検索機能の部分については、現在でもやや苦労しているとのことでした。
MongoDBを採用したシラサギ
次は、ウェブチップス野原さんから、CMSとグループウェア機能を提供するシラサギについての紹介です。シラサギの稼働環境はLinux系OSと、Ruby、Ruby on Rails、そしてDBMSとしてMongoDBが使われています。
ここでやっぱり気になるのがMongoDBの採用理由です。実はシラサギの前にはMySQLを採用したCMSがありましたが、新しいシラサギでは前の製品と似たものになるのを避ける意味に加えて、新しい技術にも挑戦したいという開発メンバの希望も反映して、MongoDBを採用することになったそうです。
提供する機能がCMS中心だった当初には、DBMSに期待する機能は比較的シンプルなデータ投入と読み出しでDBMS自体に多様な機能を求めることはありませんでした。ただ、シラサギがグループウェア機能も持つようになってくると、機能豊富なDBMSが魅力的に見える面もあるようです。しかし、DBMSの移行には大きなパワーが必要で移行を決断するには至っていないとのことです。
開発当初にRuby on RailsとMongoDBを組み合わせた例はあったかとの質問がありました。野原さんの見解としては、おそらく無かっただろうとの回答です。開発スタート当時の技術メンバがしばらく籠もって製品開発をしたという逸話を紹介いただきました。
パネルディスカッション
OSSプロダクトの開発エンジニアの採用しやすさについての問い掛けがパネリストから出ました。プリザンターでは、DBMSスキル
シラサギの場合、開発拠点である徳島ではRuby on RailsやMongoDBのスキルのある人材を探すのは難しいのが現実で、なにかの言語や案件で
DBMSから少し視点を拡げて、DBMS以外のOSSをコンポーネントとして使うことについてはどうでしょうか。プリザンターでは、独自に開発している部分が多くあり、特にUIエンジンでは既存のフレームワークなどではなくて独自のものを作っているそうです。高速な画面描画を実現するための、サーバサイドレンダリングが行えるようにしているとのこと。
シラサギでは、全文検索機能の他に、グループウェアのカレンダー機能に他のOSSを活用しているそうです。ただ、他のOSSを採用した部分は、なかなか仕様を変えられなくなります。仕様の自由度と開発効率はトレードオフになるというのは、なるほどと思う点です。何か新たに実現したいことがある場合には、既存のOSSで使えるものがあるかを数日かけてを調べたり、組み込んで試してみるそうです。それで難しければ、気持ちを切り替えて新たに開発することにしているとのことでした。
今回のオープンソースカンファレンスはセミナーを含む全てが会場開催でしたので、オンライン配信はありませんでした。講演のスライド資料の支障のない部分については、OSSコンソーシアムのWebページで公開します。
OSSがビルディングブロックになってデジタル変革は進む(はず)@OSC東京春
2月のオープンソースカンファレンス 2025 Tokyo/
OSC大阪では、ソフトウェア開発のコンポーネントとしてのDBMSを中心にして考えました。OSC Tokyo/
- OSSとエコシステム
- レガシー刷新とコンポーネント選択
- OSS開発に他のOSSを活用
- 長年愛されるOSSの秘訣
- 〔講演者・
パネリスト〕 -
- 今村かずきさん:独立行政法人情報処理推進機構
(IPA) - 比毛寛之さん:東京システムハウス株式会社
- 内田太志さん:株式会社インプリム
- 油谷実紀さん:TIS株式会社
- 梶山隆輔:日本オラクル株式会社
- 溝口則行:OSSコンソーシアム
- 今村かずきさん:独立行政法人情報処理推進機構
この企画セミナーでは、
[MySQL]2025年1月の主な出来事
9.
なお各クライアント・
MySQL 9.2.0イノベーション・リリースでの新機能や変更点
SUPER権限が必要な場面を減らすための改良が続けられており、MySQL 9.
またコミュニティ版を含め、OpenSSL 3.
MySQL Router 9.
MySQL Shellのアップグレード・
MySQL 9.2 Enterprise Editionの機能強化
MySQL 9.
ストアド・
[PostgreSQL]2025年1月の主な出来事
1月はPostgreSQL本体の新しいリリースはありませんでした。現時点の最新バージョンは、2024年11月にリリースされた17.
第31回PostgreSQLエンタープライズ・コンソーシアムセミナー
2月21日
今回は
PostgreSQL貢献者ページに日本人5人を含む24人が新たに加わる
PostgreSQL貢献者ページには、PostgreSQLプロジェクトに長期間にわたり多大な時間と労力を費やしてきた人々が掲載されていますが、新たに24人の方々が加わり、その中には次に挙げる日本の方たちも含まれていました。
- 鳥越淳さん
(NTTデータ) - 黒田隼人さん
(富士通) - 喜田紘介さん
- 曽根壮大さん
- 高塚遥さん
(SRA OSS)
この5人の皆さんはもちろん、新たに掲載された24人の皆さん、おめでとうございます。
Azure Cosmos DB for MongoDBのエンジンがPostgreSQLベースで開発されOSSで公開
マイクロソフトは1月23日、vCoreベースのAzure Cosmos DB for MongoDBを動かすエンジンとして、PostgreSQLを元に開発したものをオープンソースとして公開しました。
このソフトウェアは
- pg_
documentdb_ :PostgreSQLでのBSONcore (Binary JSON) データ型のサポートを最適化するPostgreSQLの拡張機能 - pg_
documentdb :CRUD操作、クエリ機能、インデックス管理などのAPI提供
2025年2月以降開催予定のセミナーやイベント、ユーザ会の活動
イベントごとに利便性のあるオンライン開催や、従来通りのオンサイト
Oracle CloudWorld Tour Tokyo
| 日程 | 2025年2月13日 |
|---|---|
| 場所 | ザ・ |
| 内容 | Oracle CloudWorld Tourでは、AIを活用したビジネス価値の最大化方法、最新のクラウド技術、そして自動化による生産性・ |
オープンソースカンファレンス 2025 Tokyo/Spring
| 日程 | 2025年2月21日 2月22日 |
|---|---|
| 場所 | 駒澤大学 駒沢キャンパス 種月館 |
| 内容 | 東京地区では5年ぶりに会場にて金曜と土曜の2日間、セミナーと展示の両方のフルスペック開催になります。OSSコンソーシアムも協賛出展して企画セミナー |
| 主催 | オープンソースカンファレンス実行委員会 |
第31回PostgreSQLエンタープライズ・コンソーシアムセミナー『ソフトウェアが拓くデータ活用の未来とオープンソース戦略』
| 日程 | 2025年2月21日 |
|---|---|
| 場所 | オンライン開催 |
| 内容 | 前半は |
| 主催 | PostgreSQLエンタープライズ・ |
Oracle Cloudウェビナー - MySQLをベクトル・ストアとして活用し、セマンティック検索をする方法
| 日程 | 2025年3月5日 |
|---|---|
| 場所 | オンラインセミナー |
| 内容 | MySQL 9. |
| 主催 | 日本オラクル セミナー事務局 |


